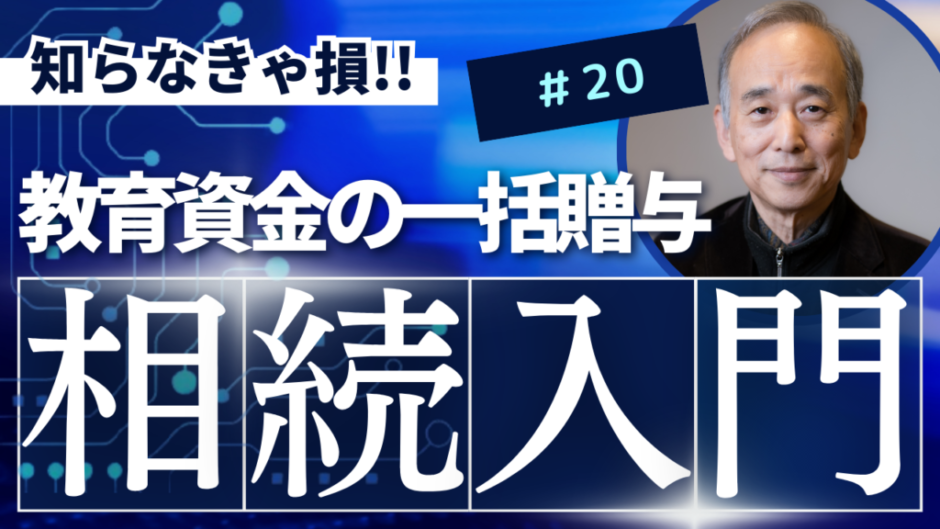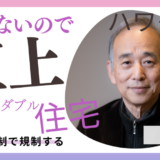贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかります。しかし、その財産の性質や贈与の目的などからみて、一定の財産については贈与税がかからないことになっています。扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものも非課税となっています。
しかし、教育費等はその都度渡さなければ非課税にならないので、不便です。それを解消する目的から「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」ができました。具体的には、受贈者は教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の人に限ります。また、贈与者は、受贈者の直系尊属である父母や祖父母などに限られます。
この制度は、受贈者が、教育資金に充てるため、金融機関等とのその教育資金管理契約に基づき、信託受益権を取得した場合等に限られます。その信託受益権または金銭等のうち、1,500万円までが、受贈者の贈与税が非課税となります。取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書の提出等をすることが必要です。
ポイントは個人間で手続きをするのではなく金融機関等で信託契約を結び一定手続きをとった場合に非課税となります。支払った授業料などの領収書を金融機関などに提出し、該当する支出であることを確認してもらう必要があります。
なお、教育資金に含まれるものは、国内又は一定の留学、インターナショナルスクールの費用です。具体的には、学校に直接支払う入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、学用品、給食、修学旅行費などが含まれます。認定こども園や保育所などを含む一定の認可外保育施設の保育料も対象となります。また習い事等をした場合の支出した金額も非課税の対象となりますが、非課税限度額は500万円となります。
なお受贈者が30歳になった時点で残っている残額は贈与とみなされ、贈与税を支払わなければなりません。その場合、直系尊属からの贈与(特例贈与)の税率ではなく、通常の贈与(一般贈与)の税率が適用されます。
契約終了時(受贈者が30歳になる)までに贈与者が死亡した場合で、教育資金で使えなかった残高は、相続税の課税対象となります。ただし、受贈者が贈与者の死亡日において、23歳未満である場合等は、相続等によって取得したものとはみなされません。
なお、令和5年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の取得をし、同日以後にその贈与者が死亡して、この非課税制度の適用を受けた場合については、税制改正がありました。その贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、その信託受益権等に対応する部分が、受贈者が23歳未満でも、相続等により取得したものとみなされます。これは、管理残額を加算する前の相続税の課税価格の合計額で判定します。
なお、教育資金を受ける受贈者が孫のである場合は相続税額の2割加算の対象者となります。
このブログを動画でチェック