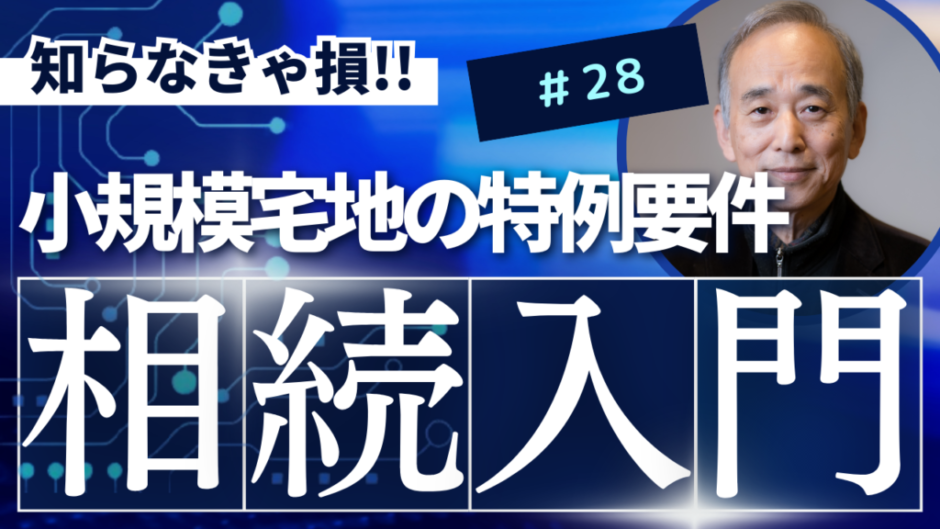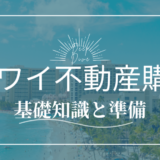小規模宅地の特例を受けるための要件は、特に居住用の場合、かなり複雑です。まず、居住要件と所有要件という言葉を説明しましょう。
所有要件から説明しますが、これは、相続人がこの特例に使いたい住居を相続税の申告期限まで所有し続けるということです。居住要件とは、所有要件だけでなく、相続人がこの特例を使いたい住居に相続税の申告期限まで住み続けるということです。申告までではなく、申告期限までであることにご注意ください。
それでは、どのような場合にどのような要件があるか、見てみましょう。
| 相続人 | 居住要件 | 所有要件 | 被相続人の要件 |
| 配偶者 | なし | なし | その宅地にある家に居住 |
| 同居親族 | あり | あり(相続開始前から) | 同上 |
| 家なき子 | なし | あり | 同上(一人暮らし) |
| 被相続人と同一生計の非同居親族 | あり(相続開始前から) | そこに居住していない |
まず、この特例を利用する住居が、被相続人が住んでいた住居と、相続人が住んでいた住居に分けます。亡くなった時、老人ホームに入所していることも多いと思いますが、以下の条件をすべて満たしていれば、自宅に居住していたとみなされます。終身利用権付きの有料老人ホームや高齢者住宅でも構いません。
- 亡くなった時に、要介護の認定を受けていた
- ホーム入所中、自宅を貸付や事業用に利用していない
- 被相続人と同一生計の親族以外が居住していない
- 同一生計の親族が勉強部屋などに使うのは良いが、空き家にはしていない
被相続人が住んでいた住居を相続することの方が多いと思いますが、それを配偶者が相続した場合は、居住要件も所有要件もありません。
子供など、配偶者以外の同居していた親族が相続する場合は、その住居を所有し続け、住み続けなければ、この特例は適用されません。もともとそこに住んでいたわけですので、この要件を満たすことは難しくはありません。
被相続人に、配偶者も同居していた親族もおらず、非同居親族が相続した場合は、居住要件はありませんので、この特例を利用するために相続した住居に引っ越す必要はありません。しかし、所有要件はあります。
ただし、相続開始前3年以内に、自分または自分の配偶者の所有する家に住んだことのない人、いわゆる家なき子に限られます。また、家なき子であっても、相続開始前3年以内に3親等内の親族や特別な関係のある法人が所有した家に住んだことのある人、住んでいる家屋を以前所有していたことがある人は除外されます。除外される場合は、可能であれば、その住宅を相続する予定の子供が、相続が近づいた時点で、被相続人と同居し始めることによって、この要件を満たすことができます。
家なき子特例要件はその他にもありますので、箇条書きにしてまとめておきます。
- 故人に配偶者も同居の親族もいないこと
- 3年以内以内に自己所有の家に住んだことがないこと
- 3年以内に3親等以内の親族の家に住んでいないこと
- 3年以内に特別な関係の法人が持つ家に住んでいないこと
- 相続開始時に住んでいる家を過去所有したことがないこと
- 10カ月以内に相続した土地を売却しないこと
被相続人と生計を一(いつ)にしていた非同居親族の住居をそのまま相続した場合は、居住要件も所有要件もあります。これは、親から離れ、親の所有する分譲マンションに住んでいる大学生が、そのマンションを相続する場合などです。通常その相続人は、今まで住んでいた家に住み続けますので、特に問題はないでしょう。
事業用宅地
事業用宅地の特例を受けるための被相続人と相続人の要件は、以下の通りです。
- 被相続人、又は被相続人と生計を一にする親族が、その宅地を事業に使用していたこと
- 相続人が、相続税の申告期限まで、その宅地を事業に使用し、所有し続けること
- 同族会社貸付用宅地の場合は、株式要件、役員要件などを満たしていること
被相続人が亡くなってから転業した場合は適用されません。しかし、古い事業の一部が継承されていれば大丈夫です。一部が継承されているかどうかが微妙な場合は、専門家にご相談ください。
なお、被相続人が亡くなる前3年以内に事業に使用し始めた宅地は、減額特例はありません。被相続人がもうすぐ亡くなることを予想して、節税のために何らかの事業を始めても、3年以内に亡くなれば、認められません。しかし、事業に使用している減価償却資産の価額が、宅地の相続時の評価額の15%以上であれば、認められます。それだけの資産を投下して始めた事業であれば、節税目的で始めたものではないとみなされるからです。
同様に、被相続人が亡くなる前3年以内に貸し付けを始めた宅地は、減額特例はありません。しかし、それ以前から事業規模でほかの宅地の貸付を行っていた場合は、相続した宅地の貸付を始めたのが3年以内であっても、減額特例を受けることができます。
特殊な例
複数の人が事業・居住用宅地を相続する場合は、相続人ごとに判定します。事業に関係ない相続人は特例の対象外です。住居用の場合、そこに住まない相続人は、配偶者や家なき子でないかぎり、特例対象外です。
被相続人の土地に二世帯住宅を建てて、親子が住んでいた場合は、建物が共同登記であれば認められます。区分登記であっても、同一生計であれば認められますが、そうでなければ認められません。
賃貸用の建物の一部に住んでいた場合は、自家用に使っていた面積が全体に占める割合に応じて、評価額を計算し、その部分に関してはこの特例を適用できます。賃貸用のスペースがたまたま空室になっていても、それを自宅の一部として計算することはできません。
居住用の宅地が複数ある場合は、主たる住居にのみ適用されますので、毎週のように使っていたとしても、別荘は認められません。しかし、夫婦が別居していた場合は可能です。
この特例は、申告までに分割しなければなりませんが、適用されないまま申告し、申告期限後3年以内に分割した場合は、適用されます。申告期限後3年以内に分割できない事情があり、それが税務署長から認められた場合は、その事情がなくなった日から4か月以内に分割すれば、適用されます。その場合は、遺産分割から4か月後以内に更正請求することが必要です。
このブログを動画でチェック