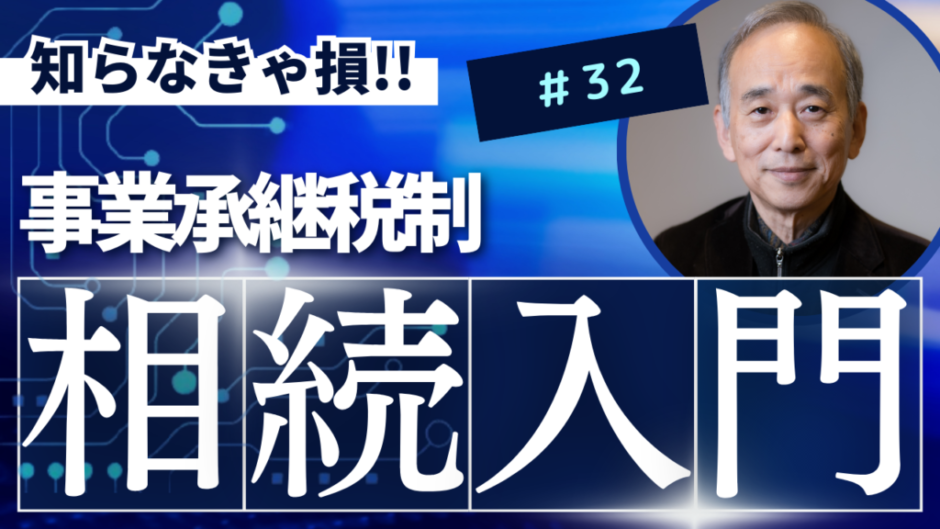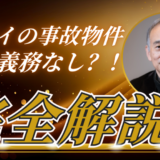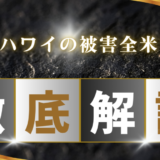事業承継には、以下の三つのケースがあります。
- 親族内事業承継
- 社内事業承継
- M&Aによる事業承継
社内事業承継やM&Aの場合は自社株を売却しますので、納税のための現金がないと言うことはありません。しかし、親族内事業承継の場合、後継者が相続税あるいは贈与税を支払わなくてはなりません。特に、経営が右肩上がりの会社は、株価が高く評価され、予想以上の納税をしなければならなくなることも多々あります。
例えば、事業主の親から5千万円の自社株の贈与を受けたとすると、特例贈与であっても贈与税は2,049万5千円で、実効税率が40%を超えます。しかも現金納付のため、せっかくもらった株の一部を処分しなければならなくなるかもしれません。
相続の場合も同じです。相続税の納税資金の準備ができていればいいですが、被相続人が急死したような場合など、銀行からお金を借りて相続税を納税することも珍しくありません。
このような問題を避けるため、2009年度の税制改正で、「事業承継税制」が創設されました。これにより、納税猶予が設けられ、一定の条件を満たすと、猶予された税金が最終的に免除されます。
また、2018年の税制改正では、さらに特例措置が設けられ、10年間の限定処置として、要件が緩和されました。特例承継計画を提出し、2018年1月1日から2027年12月31日までに、会社の株式を贈与・相続により後継者へ渡した場合、贈与税または相続税が100%猶予されます。現在のところ、特例承継計画の提出期限は2026年3月31日までとなっています。また、2019年の税制改革では、個人事業主向けの事業承継税制も設けられました。
事業承継税制を活用すると、一定の条件を満たすことによって自社の非上場株にかかる相続税や贈与税の納税猶予が始まります。その後も、一定期間、一定の要件を満たすと、猶予された税額が全額免除されます。
事業承継税制の一般処置と特例処置は、それぞれ、猶予される税額や対象となる株数などが異なります。以下はこの二つの処置の主な違いを簡潔にまとめて表にしたものです。
| 一般措置 | 特例措置 | |
| 対象株式 | 発行済議決権株式総数の2/3分まで | 全株式 |
| 適用期限 | なし | 2027年12月31日まで |
| 特例承継計画の提出 | 不要 | 必要 |
| 納税猶予割合 | 贈与100%、相続80% | 100% |
| 後継者 | 筆頭株主である後継経営者1人のみ | 持ち株10%以上の後継経営者3人まで |
| 雇用確保要件 | 5年平均で相続・贈与時の雇用の80%以上を維持 | 実質撤廃 |
| 相続・贈与から5年後以降の減免要件 | 民事再生や会社更生の際は、その時点での評価額で相続税・贈与税を計算し直し、超過分の猶予税額を免除 | 「経営環境の変化を示す一定の要件」を満たす場合、譲渡や合併で消滅・解散した場合でも、一般措置同様の減免可能 |
事業承継税制のデメリット
事業承継税制には、このようなメリットだけでなく、デメリットもありますので、慎重に決断する必要があります。
事業承継税制のメリット
既に述べたように、通常の事業承継では、株価に応じた税金を納めなければなりませんが、この税制を利用することによって、それが猶予あるいは免除されます。また、特例処置を活用する場合は、3人まで後継者に承継することができますので、共同経営にして、後継者候補間での争いを避けることができます。従業員などを後継者にする場合も、親族外承継が可能です。
事業承継税制のデメリット
納税猶予期間中に規定の取り消し事由が発生した時は、猶予されていた税額だけでなく、その利子も支払わなければなりません。取り消し事由は、贈与の場合も相続の場合も、20以上ありますので、それに該当することが起きないよう、くれぐれもご注意ください。以下は、主な取り消し事由をまとめたものです。これについては、国税庁および中小企業庁の公式サイトをご覧ください。
- 後継者が代表者を退任した(精神障害や身体障害、要介護などやむを得ない状況を除く)
- 同族の議決権数が過半数以下になった
- 後継者の同族関係者が後継者より多くの議決権数を保有することになった
- 納税猶予対象株式を譲渡した
- 総収入がゼロになった
- 資本金や準備金が減少した
また、免除が決定されるまでの期間が長く、特例承継計画が認定された後も、定期的に都道府県や税務署への報告をする必要があるため、手間がかかります。事業承継税制は非常に複雑な制度ですし、間違った場合に納税額に与える影響が多大ですので、自分でするのは間違いのもとです。税理士などの専門家の助けを求めてください。
事業承継税制の手続き
事業承継税制の手続きは、以下の通りです。
相続税のケース
- 特例措置を活用する場合は、特例承認計画を都道府県庁に提出する
- 相続開始後、8ヵ月目までに都道府県庁に事業承継税制の申請をする
- 審査後、都道府県庁から認定書が交付される
- 認定書の写しを添付して相続税の申告書等を税務署に提出する
- 納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提供し、税務署に申告する
最後の担保ですが、特例を受ける非上場株式を担保にすることができます。この過程を経て納税猶予が始まりますが、それで終わりではありません。
最初の5年間は
- 都道府県庁へ年1回「年次報告書」を提出する
- 税務署へ年1回「継続届出書」を提出する
5年経過後は
- 税務署へ3年に1回「継続届出書」を提出する
最初の5年が経過した後、次の後継者に「猶予継続贈与」をすると、相続税が免除されます。また、5年経過前にやむを得ない理由で代表権をなくし、「猶予継続贈与」をして、さらに5年経過後に会社が破産した、あるいは清算した場合、または後継者が亡くなった場合も、相続税が免除されます。
贈与税のケース
贈与税の納税猶予手続きも、基本的に相続の場合と同じです。都道府県庁に事業承継税制の活用を申請する期限は、贈与した翌年の1月15日までです。納税猶予期間が始まってからの手続きや納税が免除される要件も、基本的に相続の場合と同じです。ただし、納税猶予期間中に先代の経営者が亡くなった場合、贈与税は免除されますが、相続税が発生する可能性があります。その場合は、相続税の納税猶予に切り替えることができます。
事業承継税制を活用するための条件
事業承継税制には厳しい要件が定められています。相続税と贈与税の要件は、以下の通りです。
1.先代経営者が満たすべき条件
- 会社の代表者であった
- 相続開始または贈与の直前に、現経営者親族などで総議決権数の過半数を保有しており、筆頭株主であった
- 贈与の場合、贈与時に代表者を退任している(有給役員として残ることは可)
2.後継者が満たすべき条件
- 相続開始または贈与時、後継者と後継者親族などで総議決権数の過半数を保有することになる
- 後継者が1人なら、最も多くの議決権数を保有することになる。後継者が2人または3人なら、総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、後継者と特別の関係がある者の中で最も多くの議決権数を保有することになる
- 贈与の場合、贈与時に18歳以上 で、贈与の直前で3年以上(特例措置の場合は贈与の直前において) 役員であり、代表者である
- 相続の場合、原則として相続開始の直前に 役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者である
3.会社が満たすべき条件
- 中小企業者
- 従業員が1人以上
- 上場会社、風俗営業会社ではない
- 資産管理会社等に該当しない
4.納税猶予スタート後の条件
最初の5年間
- 後継者が会社の代表者で筆頭株主
- 後継者が猶予対象株式を継続保有している
- 雇用の8割以上を5年間平均で維持する
5年経過後
- 後継者が猶予対象株式を継続保有している
特例処置を受けていて、雇用の8割が維持できない場合、認定支援機関の指導や助言を受け、その意見を添付した報告書を都道府県庁に提出することによって、納税猶予が継続されます。
このブログを動画でチェック