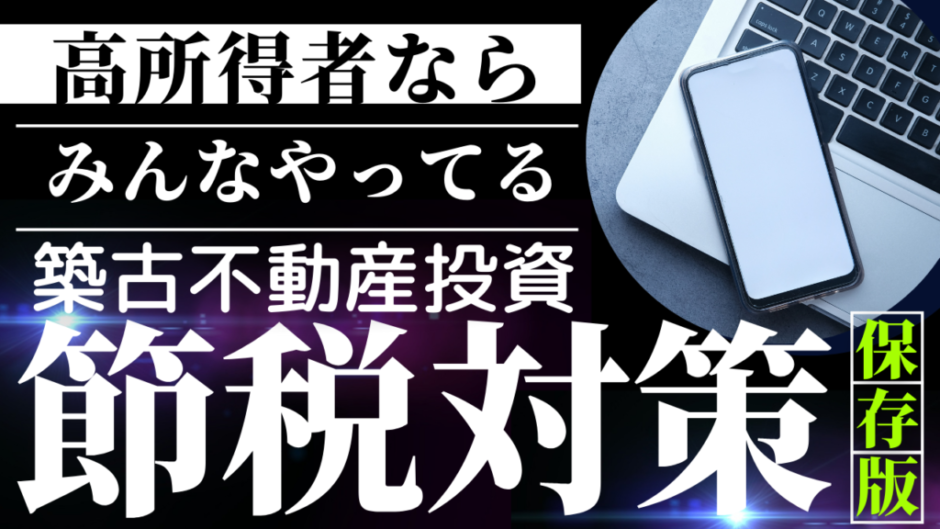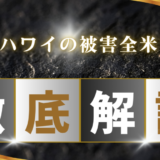年収が増えるほど、所得税・住民税の負担は重く、最高税率は約55%に達します。この税負担を合法的に軽減する手段として、高額所得者の間で注目されているのが「築古の収益不動産」を活用した投資です。これは、家賃収入だけでなく「所得税の圧縮効果」を最大限に活用し、手元に残るお金を増やす戦略です。
節税の仕組み:減価償却と損益通算
この節税スキームの核は、「減価償却」です。不動産の建物部分は、購入費用を数年間にわたって「経費」として計上できます。特に木造の「築古」物件(築22年以上)は、わずか4年で全額を経費計上できるため、短期間に多額の「帳簿上の経費」を生み出します。この多額の減価償却費により、不動産所得は帳簿上「赤字」になります。この赤字を、本業の給与所得など他の所得と合算できるのが「損益通算」です。
【具体例】
私の息子のように、本業で高い所得を得ている方が築古アパートに投資したケースを考えてみましょう。彼が私に相談してきたのは、「同僚たちが皆、築古の収益物件を購入して節税している」という話を聞き、自分も同様の策を講じたいと考えたからです。特に、都心の高級住宅地の築古マンションのペントハウスを購入して同僚に貸すという具体的な話も耳にし、その仕組みとメリット、リスクについて知りたいと強く思っていたようです。
例えば、1億円の築古分譲マンションを購入し、そのうち建物部分が6,000万円だったと仮定します。築49年以上の鉄筋コンクリート造の建物であれば、この建物部分を9年間で減価償却できますので、毎年約667万円(6,000万円の9分の1)を経費として計上できます。もしこの約667万円の赤字を給与所得などと損益通算し、ご自身の税率が55%であれば、毎年約367万円もの税金が軽減される計算です。これが「所得税の圧縮効果」です。
売却時の税率差で利益を確定「出口戦略」
このスキームは、減価償却を終えるタイミングで物件を売却して完成します。売却益(譲渡所得)は、給与所得とは合算されず「分離課税」で計算されます。物件の所有期間が5年を超えれば「長期譲渡所得」となり、税率は所得税・住民税合わせ約20%と、給与所得の最高税率(約55%)に比べ格段に低く設定されています。
減価償却で免れた55%の税金と、売却益にかかる20%の税金の差、約35%が実質的な利益となるのです。これは単なる税金の繰り延べではありません。個人で行う方が、法人よりもこの税率差を大きく享受できるため有利です。法人の場合、事業で得た利益も不動産を売却して得た利益も、原則として同じ法人税率で課税されるため、個人で実行したときのような劇的な税率差は生まれません。
まとめと注意点
「築古不動産投資による節税スキーム」は、以下のステップで手元資金を最大化します。
- 購入: 築古木造物件で短期に多額の減価償却費を計上。
- 損益通算: 不動産赤字を給与所得などと合算し、高い税率の所得を圧縮。
- 売却: 減価償却終了後(5年超)に売却し、低い税率で譲渡所得税を納める。
ただし、成功には物件選びの専門知識が不可欠です。空室・修繕リスク、税制改正リスクも考慮し、興味があれば専門家にご相談ください。