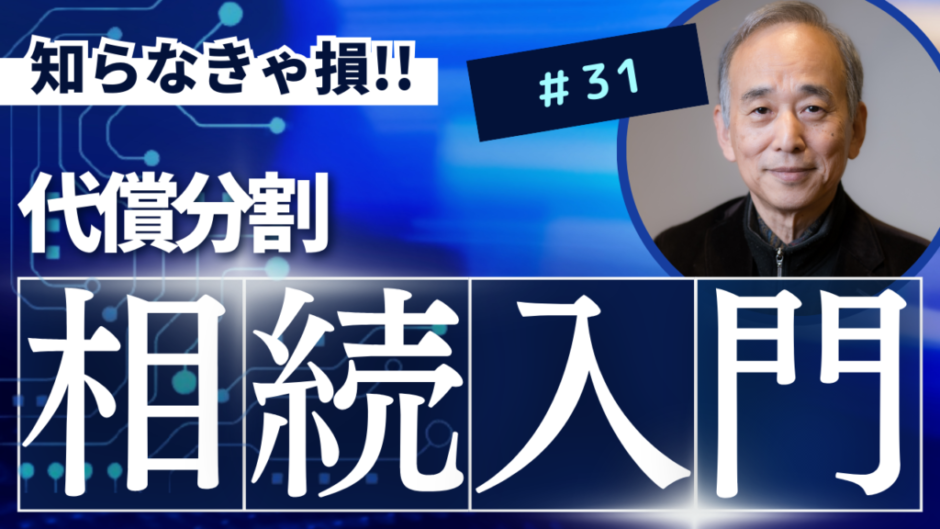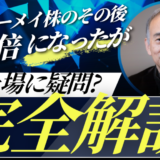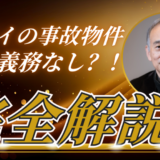31. 代償分割
遺産がすべて流動資産であれば、複数の相続人に平等に分けることは簡単です。しかし、実際には土地建物など、分割できないものもあります。遺産分割には四つの方法がありますので、うまく使って相続争いを避けることが重要です。
- 現物分割
これは、現物を相続人にそのまま分けることです。例えば、相続人が二人いる場合、一人に自宅、もう一人に株と預金をそれぞれ相続させます。簡単ですが、これだけでは公平に分けられないことが多いという欠点があります。 - 換価分割
そこで、自由に分けられない固定資産を売って、お金にして分けようと言うのが換価分割です。しかし、事業用の資産など、売ってしまったら事業承継ができなくなってしまうものもあります。また、売却によって譲渡所得税がかかることもあります。 - 共有とする分割
そこで、例えば家を売らないで、複数の相続人の持ち分を決めて共有することもできます。しかし、全員の同意がなければ何もできない状態になりますので、将来の争いの元です。 - 代償分割
最も合理的なのが代償分割です。例えば、兄と弟が6,000万円の家と4,000万円の流動資産を相続するとします。兄が家を相続し、弟に1,000万円支払えば、公平な分割になります。この1,000万円に贈与税はかかりません。兄が1,000万円持っていなければできませんが、分割払いにすることは、弟が納得さえすれば可能です。現金の代わりに株や、あるいは1,000万円の価値がある何か他の物を譲渡することもできますが、その場合は譲渡所得税がかかります。
実勢価格と課税評価額
どのような形で分けるにしろ、通常、時価、つまり実勢価格に沿って分割することが多いです。特定の遺産の実勢評価額がいくらであるかは、特に法律によって決められた評価方法はありませんので、分割協議において合意する必要があります。
しかし、時価と課税評価額は、金融資産は同じですが、不動産などは異なる場合が多いです。そうすると、時価で平等に分割しても、支払う相続税が異なるため、それを調整しないと不公平です。特に、都市部の不動産は相続税評価額が時価の半分以下などということもありますので、相続税が他よりずいぶん低くなることがあります。調整するかどうか、あるいは最初から課税評価額に基づいて分割するかなどは、相続人の自由です。
不動産の価額
不動産は、通常、遺産の大きな部分を占めますので、これをどう評価するかがよく問題になります。最も正確で皆さんが納得できる方法は、鑑定士に頼むことですが、それには費用が掛かります。話し合って合意しても構いませんし、不動産業者に聞くのもよいでしょう。また、特に地方では、地価の下落で相続税評価額と実勢価額の差が縮まっていますので、相続税評価額を使っても構いません。
なお、不動産についてここでついでに述べておきますが、住宅ローンは、通常、団体信用生命保険が義務付けられています。被相続人が亡くなれば、その保険で残高が支払われますので、負債を相続する必要はありません。
不動産に限らず、負債は、通常それに関連する遺産を相続した人が負債の支払いもすることが多いです。例えば、車を相続した人が車のローンも支払うと言うのが一般的ですが、だれが支払うかは明確にしておくべきです。法的には相続人全員の負債ですので、不履行になった場合、銀行はほかの相続人にもその人の相続分に従って請求するからです。ローンがある遺産を支払い能力のない相続人に相続させるべきではありません。
このブログを動画でチェック