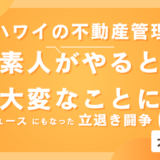「家を売りたい」と思ったら、スマホで情報を入力するだけで、数時間後には現金での買取価格が提示される――。そんなSFのような話を実現し、アメリカの不動産業界に衝撃を与えた企業があります。その名はOpendoor (ティッカーシンボル: OPEN)。
しかし、同社の物語は単なる「ハイテク不動産屋」では終わりません。巨額の赤字、株価の暴落、そして競合の撤退。一度はどん底を見たOpendoorが、2025年に入って株価が460%以上も急騰するという驚異的な復活を遂げています。私も上がり始めて間もなく買って、あっという間に倍以上になりました。
なぜ市場は再び熱狂しているのか?その裏には、Eコマースの巨人Shopify出身の新CEOが仕掛ける、壮大な「革命」のシナリオがありました。Shopifyとは、オンライン/実店舗で商品を販売したい事業者に、店舗構築ツール・決済・物流・マーケティング・分析などをワンストップで提供するプラットフォーム型事業です。
革命前夜:iBuyerモデルの光と影
Opendoorが発明した**「iBuyer(アイバイヤー)」**という仕組みは画期的でした。従来の不動産売却にあった、こんな面倒をすべて解消したのです。
- いつ売れるか分からないという不確実性
- 数ヶ月に及ぶ長い売却期間
- 週末ごとの内覧対応の手間
売り手は、Opendoorの提示額に納得すれば、好きなタイミングで家を売却できます。この「スピード」と「確実性」は絶大な価値を持ち、同社は一気に市場の寵児となりました。
しかし、その裏側でビジネスモデルの脆さも露呈します。自社で住宅を大量に仕入れるため、常に莫大な在庫リスクを抱えなければなりません。金利が上昇し、不動産市況が悪化すると、在庫の価値は下落し、巨額の損失が発生します。事実、同じモデルを採用していた競合のZillowは巨額の赤字を出して事業から撤退。Opendoor自身も2022年には14億ドルもの純損失を計上し、株価はピーク時から98%も暴落しました。
市場はOpendoorに「ゲームオーバー」の烙印を押しかけていました。しかし、そこからが本当の革命の始まりだったのです。
第2幕:不動産取引の「OS」になるという野望
転換の旗手となったのが、Shopifyの元COO、Kaz Nejatian氏です。彼が新CEOとして掲げたのは、単なる不動産転売ヤーからの脱却でした。目指すのは、不動産取引のあらゆるプロセスを支える**「AIプラットフォーム」、つまり不動産取引の“OS”**になることです。
これは、ShopifyがEコマースの世界で成し遂げたことと全く同じです。Shopifyは自ら商品を売るのではなく、誰でもオンラインで商売ができるための「道具」と「舞台」を提供しています。
Opendoorが目指す未来も、まさにこれです。
- AI価格査定エンジンを外部に提供: 自社の買取リスクを最小化するだけでなく、超高精度なAI査定機能を、銀行や他の不動産会社にサービスとして販売する。
- マーケットプレイス化: 自社で在庫を抱えるのではなく、Opendoorのプラットフォーム上で、他の不動産会社や投資家が自由に住宅を売買できる市場をつくる。Opendoorは取引ごとに手数料を得る「場代ビジネス」に転換する。
- ワンストップ・エコシステム: 住宅ローン、保険、リフォーム、引越しまで、取引に関わるあらゆるサービスを自社プラットフォームに統合し、利用者にシームレスな体験を提供する。
つまり、**「不動産を売買する会社」から、「不動産の売買をしたい人たちをテクノロジーで支援する会社」**へと生まれ変わろうとしているのです。市場がOpendoorの株価を再評価し始めたのは、この壮大なビジョンが、Shopifyという成功事例を持つ新CEOによって語られたからに他なりません。投資家は、もはやOpendoorを赤字の不動産会社ではなく、**将来SaaS(Software as a Service、ソフトウェアを自社でインストールせずインターネット経由で利用する形態)企業のような高い利益率を叩き出す可能性を秘めた「AIテック企業」**として見始めたのです。
最終章:この革命は、日本にもやってくるのか?
さて、ソフトバンクはOpendoorの大株主です。孫氏は、この革新的なモデルを日本に持ち込むつもりはないのでしょうか。
1. 「骨抜き」に終わった2025年の法改正
当初、業界の悪弊「囲い込み」を罰する2025年の法改正が、Opendoorのような透明性の高いモデルの追い風になると期待されていました。しかし、この改正は事実上の「骨抜き」であったとの見方が支配的です。なぜなら、罰則が最も軽い「指示処分」に留まるという点に加え、より大きな問題が存在するからです。
媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約があります。法改正後も、複数の不動産会社と契約できる「一般媒介契約」の場合、物件情報をレインズ(不動産情報ネットワーク)へ登録する義務がないのです。
両手取引を狙う業者は、売主にこの契約形態を勧めることで、合法的に情報を「囲い込み」、自社だけで顧客を見つけようとすることが依然として可能です。これでは、市場の透明性を高めるという本来の目的は達成できません。
2. 去ってしまった孫正義氏の関心
ソフトバンク・ビジョン・ファンドが2018年にOpendoorへ出資した事実は、日本展開への期待を抱かせました。しかし、重要なのは現在の**「関心」のありか**です。投資自体は継続しているかもしれませんが、現在の孫正義氏とソフトバンクグループの経営資源と戦略的関心は、完全に生成AIへとシフトしています。
近年、彼らがOpendoorの日本展開について具体的な関心を示したことは一度もありません。Yahoo!不動産、PayPay、LINEとの連携というシナリオも、今となっては現実味のない「夢物語」なのかもしれません。
3. 変化を拒む、業界の「見えない壁」
これが最も根深い問題です。日本の不動産業界は、業界団体を中心とした旧来の商慣習が根強く、デジタル化による透明性の向上は、既存の仲介業者の利益を脅かすため、激しい抵抗に遭ってきました。監督官庁からの「天下り」に象徴されるような、旧態依然とした構造がイノベーションを阻み、Yahoo!不動産でさえ大きな変革を起こせずにいます。この高く、厚い壁の前では、海外の破壊的モデルも無力化されてしまうのです。
弊社の河野社長も、米国のMLS(米国版レインズ)を国交省の方と見学に行ったことがありました。その後、その方は、日本にもこれを取り入れるために取り組んだそうですが、すぐに他の部署に移されてしまったそうです。しかも、同じことを試みた別の方も同じ目に合ったそうです。不動産業界には、FRK(不動産流通経営協会)という団体があり、官僚の天下り先になっています。この癒着が日本の進化を妨げているのです。
まとめ:これは「対岸の火事」ではなく「日本の課題」
Opendoorの物語は、刺激的ですが、今の私たちにとっては「日本の不動産業界が抱える課題の根深さ」を浮き彫りにする**『反面教師』**と言えるでしょう。
私たちが問うべきは、「黒船はいつ来るのか?」ではありません。「なぜ、日本からOpendoorのようなイノベーションが生まれないのか?」です。その答えは、効果の薄い規制と、変化を拒む業界構造という、厳しい現実の中にあります。日本の不動産市場の変革は、外部の誰かが起こしてくれるわけではありません。この国の構造的な課題と、私たち自身が向き合うことからしか始まらないのです。
このブログを動画でチェック