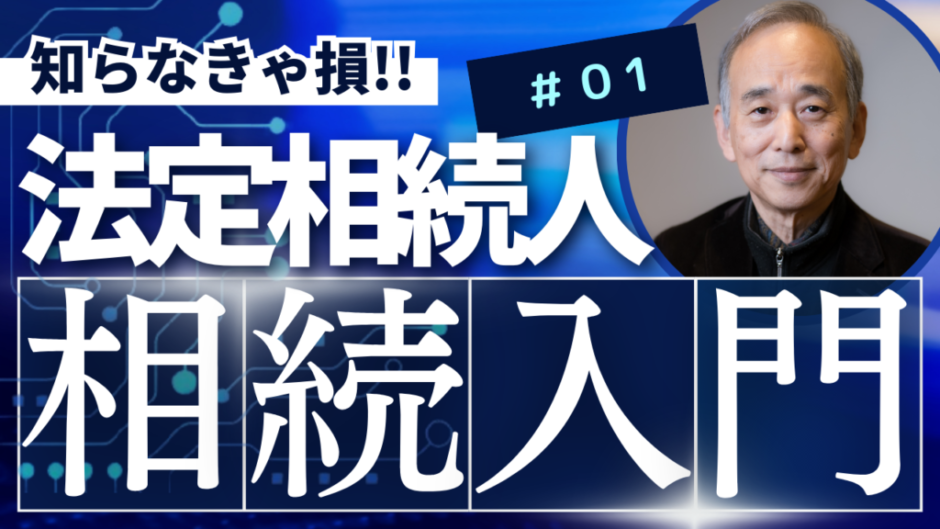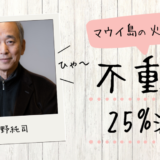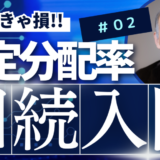民法は、相続する権利を持つ人を決めており、それを法定相続人と呼びます。しかし、実際の相続は、法定相続人が全員相続する、それ以外の人は遺産を取得できない、というわけではありません。ただし、法定相続人以外が遺産を取得する場合は、相続ではなく、遺贈です。
誰がどれだけ遺産を取得するかは、遺言や、法定相続人全員による遺産分割協議で決めることもできます。したがって、法定相続人だけれど相続しない、法定相続人でないけれども遺産を取得する、ということはよくあります。
では、法定相続人とは誰でしょう。まず、配偶者がいる場合は、必ず法定相続人になります。それ以外の法定相続人は、第一順位、第二順位、第三順位の順に相続権を持ちます。第一順位の相続人がいなければ第二順位、それもいなければ第三順位となります。しかし、配偶者がいないのでその代わりにだれかが相続するということはありません。その違いのゆえに、配偶者は第一順位とはみなされません。
第一順位は、被相続人の子供です。配偶者のいる、いないに関係なく、子供が第一順位の法定相続人です。子供が亡くなっているが、その子の子供、つまり孫がいる場合は、孫も法定相続人になりますし、孫も亡くなっていれば曾孫が法定相続人になります。曾孫も亡くなっていれば、玄孫、来孫、昆孫、仍孫、雲孫と続きますが、まあ、そんなことはないでしょうね。前妻は配偶者ではありませんが、前妻との間にできた子や、養子も、第一順位です。
子供、あるいはその子孫がいない場合、つまり第一順位に当たる人がいない場合は、第二順位の人が法定相続人になります。第二順位に当たるのは被相続人の父母です。滅多にありませんが、父母のいずれも亡くなっているが、祖父母が生存している場合は、父母の代わりに祖父母が法定相続人になります。
第一順位も第二順位もいない場合は、第三順位に当たる人が法定相続人になります。第三順位とは、被相続人の兄弟です。亡くなっている兄弟に子供がいる場合、つまり被相続人から見て甥や姪がいる場合は、彼らも法定相続人とみなされますが、甥や姪も亡くなっていて、その子供がいる場合は、法定相続人にはなりません。第一順位はどこまでも下りますし、第2順位もどこまでもさかのぼりますが、第三順位は甥や姪の子供には下りません。
配偶者で法定相続人になれるのは被相続人の配偶者のみです。亡くなった子供の配偶者は、その子の子供、つまり孫がいなくても、法定相続人になることはありません。同じことが、孫、兄弟、甥、姪の配偶者についても言えます。父母や祖父母も、直系尊属でなければなりませんので、義理の関係では法定相続人にはなりませんが、養子縁組をしていればなります。
上記に当てはまる人が誰もいない天涯孤独な方が亡くなった場合、特別縁故者からの請求がない限り、その財産は国庫に帰属します。特別縁故者とは、法定相続人以外で、被相続人の介護をした方など、特別な縁故がある人ですが、それについてはまた別のビデオで詳しく説明します。
法定相続情報一覧図
相続において、誰が法定相続人であるかを証明しなければならないことがよくあり、そのたびに戸籍などをそろえるのは大変です。この問題を避けるために法定相続情報一覧図を作成し、法務局のお墨付きをもらうことができます。その場合、相続人の住所は記載しなくても作成できますが、住所がないととても不便ですので、最初から入れておくようにしてください。
特異なケースですが、日本国籍を喪失している相続人はこの制度を利用することができません。日本国籍で外国に住んでいる方は、この制度を利用できますが、住民票が取れませんので、法定相続情報一覧図に住所を記載できません。しかし、領事館などからの在留証明を添付すれば大丈夫です。
法定相続情報一覧図を作成すること自体が面倒だという方は、税理士などに代理人として作成してもらうことができます。
このブログを動画でチェック